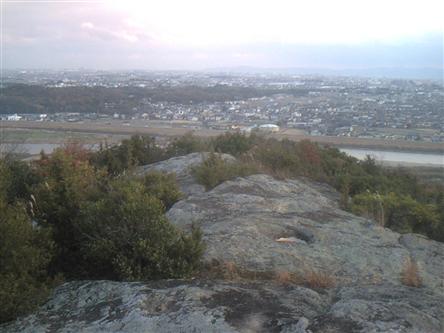| 1.コース |
加古川の北に平荘湖という人造湖があり、それを取り巻くようにいくつかの低山がある。それらをいくつか登ってみた。
また、日岡駅前の日岡山の三角点も前回未発見だったので探してみた。
日岡山は山頂に、日本武尊の母君の御陵があり周辺はスポーツ&史跡公園となっている。
こちらの古墳群は以前訪問したので訪れるのは割愛。
加古川を渡り、変電所のあたりから入山。露岩尾根を徐々に高度を上げる。
青少年館方向へ降りるが、こちらもかなり急な岩場。ところどころロープが張ってある。
岩場下りに気になっているうちに道を誤り少年自然の家に降りてしまう。
どうやら立ち入り禁止らしいが、ごめんちゃいして、無人のフィールドアスレチックを横切る。
古墳がいくつかあるという青少年館前まで行ったが、お目当ての湖畔にある露出した石室は危険防止のためか、工事用フェンスで囲まれ悲惨な状況。
湖畔の対岸の第三堰堤付近から升田山に入山。最初の上り以外はしばらくなだらかな尾根歩きが続く。
この尾根沿いにはいくつか古墳があり、看板が立っているがほかの林と区別がつかない。
古墳が絶えたと思ったら、露岩地帯となり一気に岩場を昇ったら升田山。
ここからの降りる道は八十の岩橋と呼ばれ、イザナギ、イザナミを始め諸神が降臨した道らしい。
劇下りの岩場で、無事降りた私は降臨とは程遠い状態。
いずれも低い山でしたが、播磨平野から淡路までも見渡せる風景は絶景でした。
|
|
距離 |
最高標高 |
最低標高 |
| JR日岡駅 |
| | |
| 0.6km |
ca35m |
ca10m |
| 日岡陵 |
| 0.2km |
50.9m |
ca35m |
| 日岡山 |
| 1.4km |
50.9m |
ca10m |
| 池尻橋 |
| 1.8km |
ca15m |
ca10m |
| 里古墳 |
| 1.9km |
216m |
ca15m |
| 飯盛山 |
| 1.2km |
216m |
ca40m |
| 少年自然の家 |
| 0.8km |
ca40m |
ca30m |
| 青少年館 |
| 2.4km |
105.08m |
ca30m |
| 升田山 |
| 0.4km |
105.08m |
ca10m |
| 神姫バス・池尻ダム口バス停 |
|
|
|
|
|
| 2.山と基準点 |
| 山名 |
基準点名 |
基準点コード |
等級種別 |
20万分の1 |
5万分の1 |
標高 |
備考 |
| 日岡山 |
日岡山 |
TR45234163801 |
四等三角点 |
姫路 |
高砂 |
50.95m |
|
| 飯盛山 |
|
|
|
|
|
216m |
|
| 升田山 |
上ノ山 |
TR35234164801 |
三等三角点 |
姫路 |
高砂 |
105.08m |
|
|
|
| 3.史跡 |
| 名称 |
種類 |
全長 |
被葬者・他 |
| 褶墓古墳 |
前方後円墳 |
80m |
景行天皇皇后播磨稲日大郎姫日岡陵 |
| 日岡山古墳群20号墳 |
円墳 |
?m |
|
| 里古墳 |
前方後円墳 |
45m |
|
| 平荘古墳群池尻21号墳 |
円墳 |
6m |
|
| 平荘古墳群池尻6号墳 |
石室露出 |
- |
|
| 平荘古墳群升田山15号墳 |
円墳 |
13.5m |
|
|
|
| 4.写真 |
| ■日岡駅前 |
 |
| 柵に囲まれた不思議な橋 |
| ■日岡神社 |
 |
| 安産の神様 |
| ■日岡陵 |
 |
| ヤマトタケルのお母さんのお墓 |
| ■日岡山古墳群20号墳 |
 |
| 看板がないとわからん |
| ■日岡山 |
 |
| 三角点がひっそり |
 |
| 山頂から、加古川市街地方向 |
 |
| 加古川上流方向、田園が広がる |
| ■池尻橋 |
 |
| 一番高いところが飯盛山 |
| ■里古墳 |
 |
| 小さいながら前方後円墳ってわかる墳形 |
| ■飯盛山 |
 |
| 痩せ尾根を登っていきます |
 |
| 飯盛山山頂 |
 |
| 山頂からの眺め |
 |
| 降り口も岩だらけ |
| ■平荘古墳群 |
 |
| 池尻21号墳 |
 |
| 池尻6号墳。今回の目的の一つですが、なんか無残なお姿 |
 |
| 金網の隙間から覗いてみました。満水時には水没するとか。 |
| ■升田山 |
 |
| 升田山古墳群15号墳 |
 |
| 升田山古墳群1号墳 |
 |
| 升田山古墳群2号墳 |
 |
| 升田山古墳群13号墳 |
 |
| 尾根筋から加古川 |
 |
| 反対側の平荘湖 |
 |
| 升田山山頂 |
 |
| 山頂から加古川 |
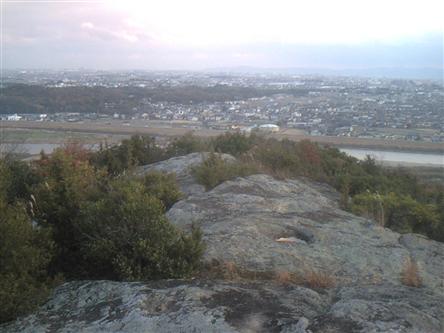 |
| 八十の岩橋 |
 |
| 八十の岩橋側ののぼり口 |
 |
| 池尻ダム口バス停から対岸の日岡山 |
|